
早く作図するコツを知りたい
こんな方に向けた記事です。
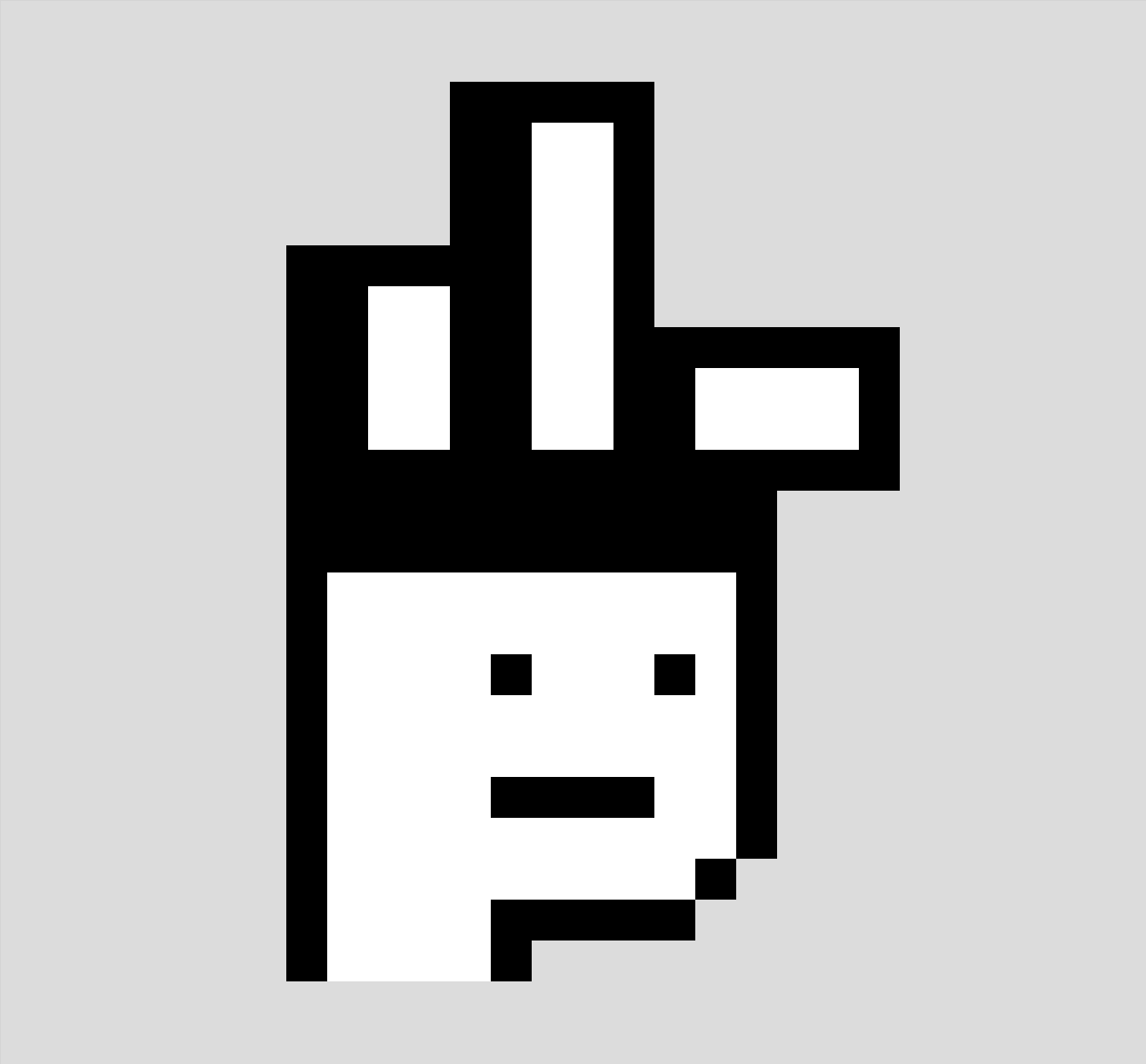
作図はちょっとした工夫で
差がつく
初受験でもコツを掴めば作図スピードは速くなります。
製図試験に合格した体験をもとに作図スピードを上げるコツを紹介します。
作図スピードを上げる方法
図面表現を覚える
まずはこれ。
作図練習を始めたばかりの頃は何から書いたらいいか分からないので手が止まってしまいます。
逆に、図面表現を覚えれば作図スピードが上がります。
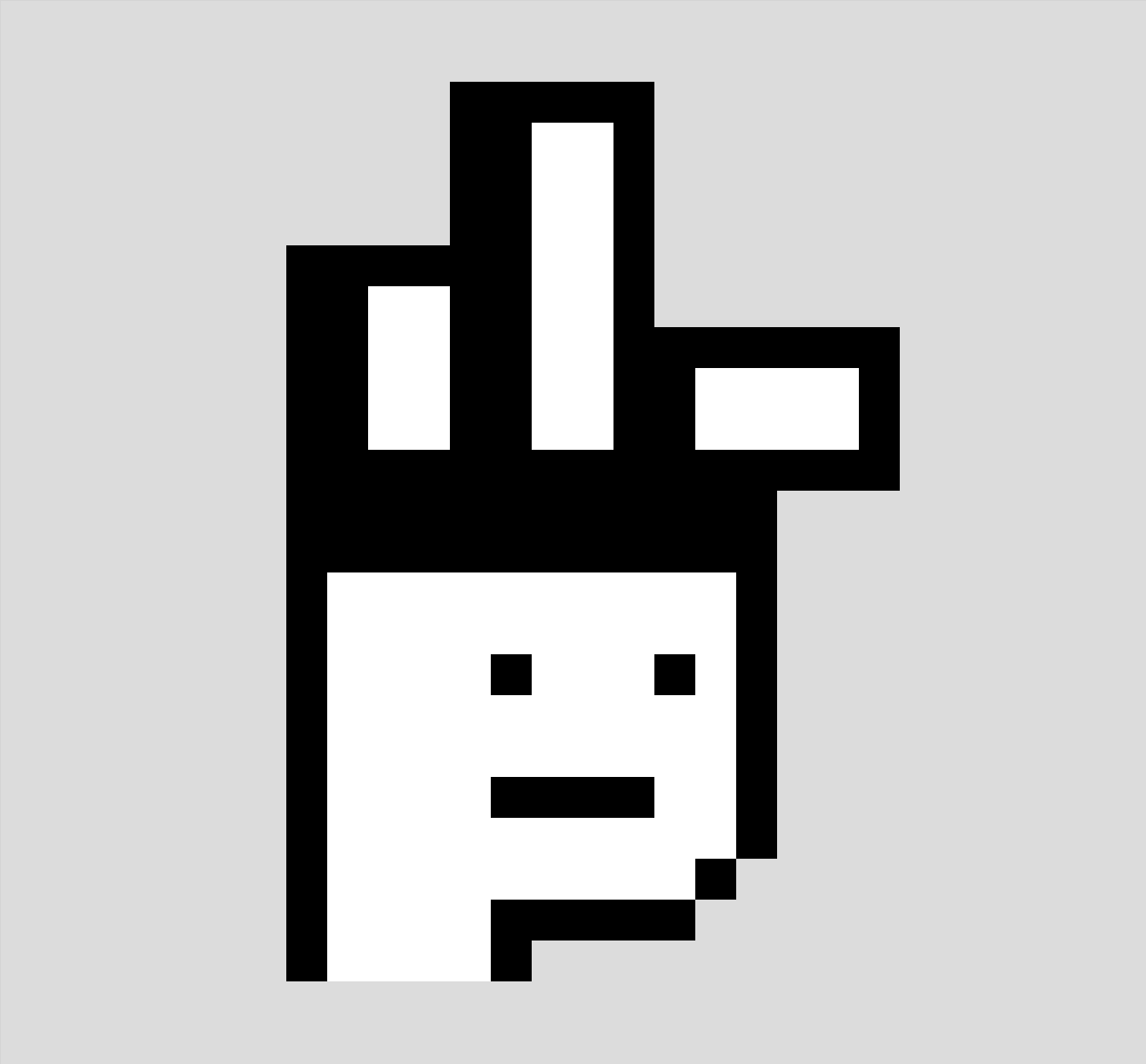
料理で例えるとレシピが
頭に入っているかどうか。
できるだけ早い段階で図面表現を覚えていきましょう。
図面表現
:階段の踏面の表現
:トイレのサイズ感
:EVの寸法
:家具のレイアウト
最初は大変だと思いますが、学科試験に合格したあなたなら大丈夫です。
また、図面表現を覚えれば作図が早くなるだけではなくエスキスにも役立ちます。
例えば階段の納め方を2パターン知っていれば部屋の配置を考えやすくなります。
資格学校では色々な課題がでます。階段やトイレの配置などの図面表現をトレースして手で覚えていきましょう。
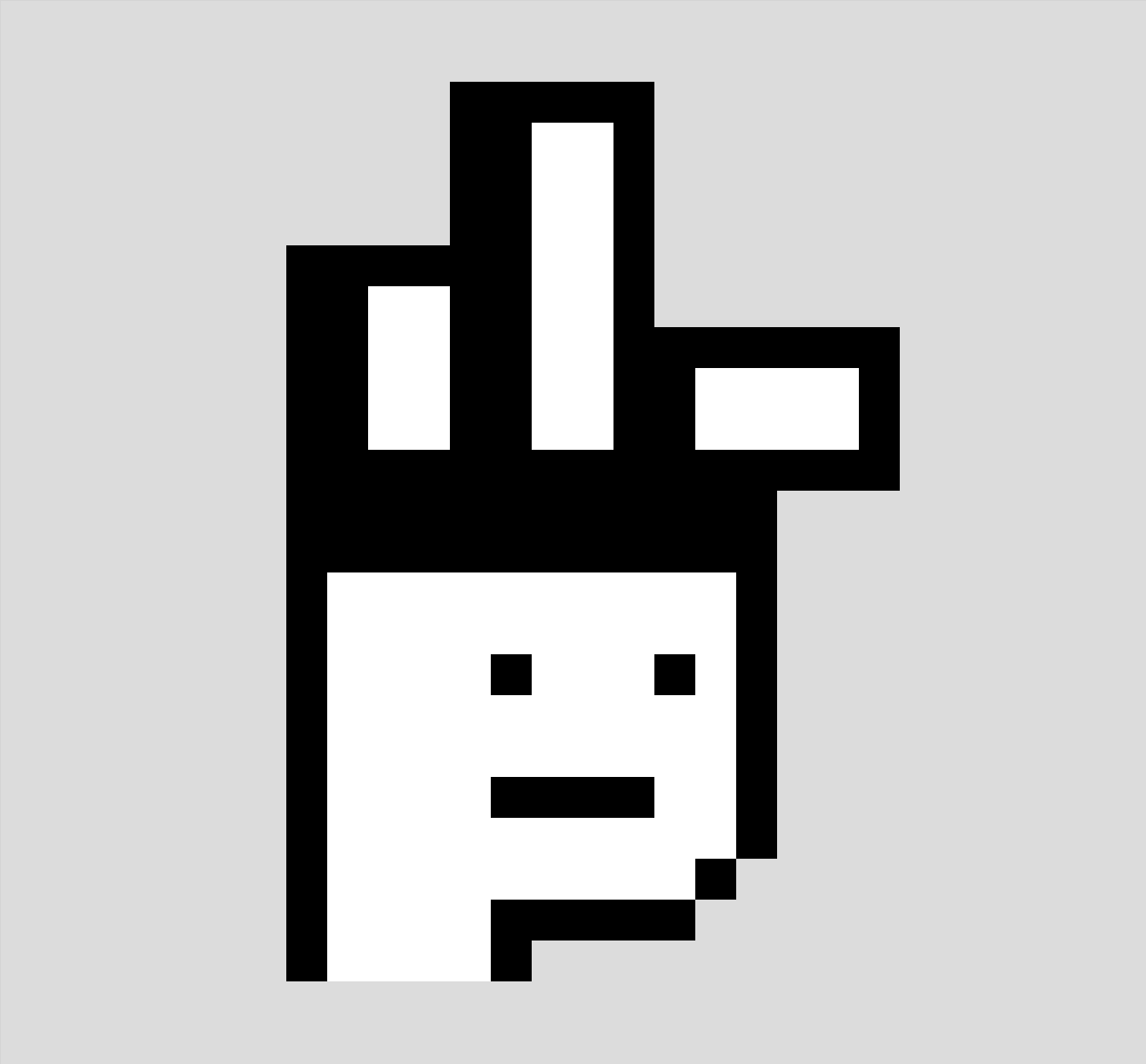
ぼくは5mm方眼用紙を
持ち歩いて会社の昼休みに
トレースをしていました。
手間はかかりますが、最も効率的に覚えられます。
フリーハンドで書く
作図スピードを早めるにはフリーハンドが最強です。
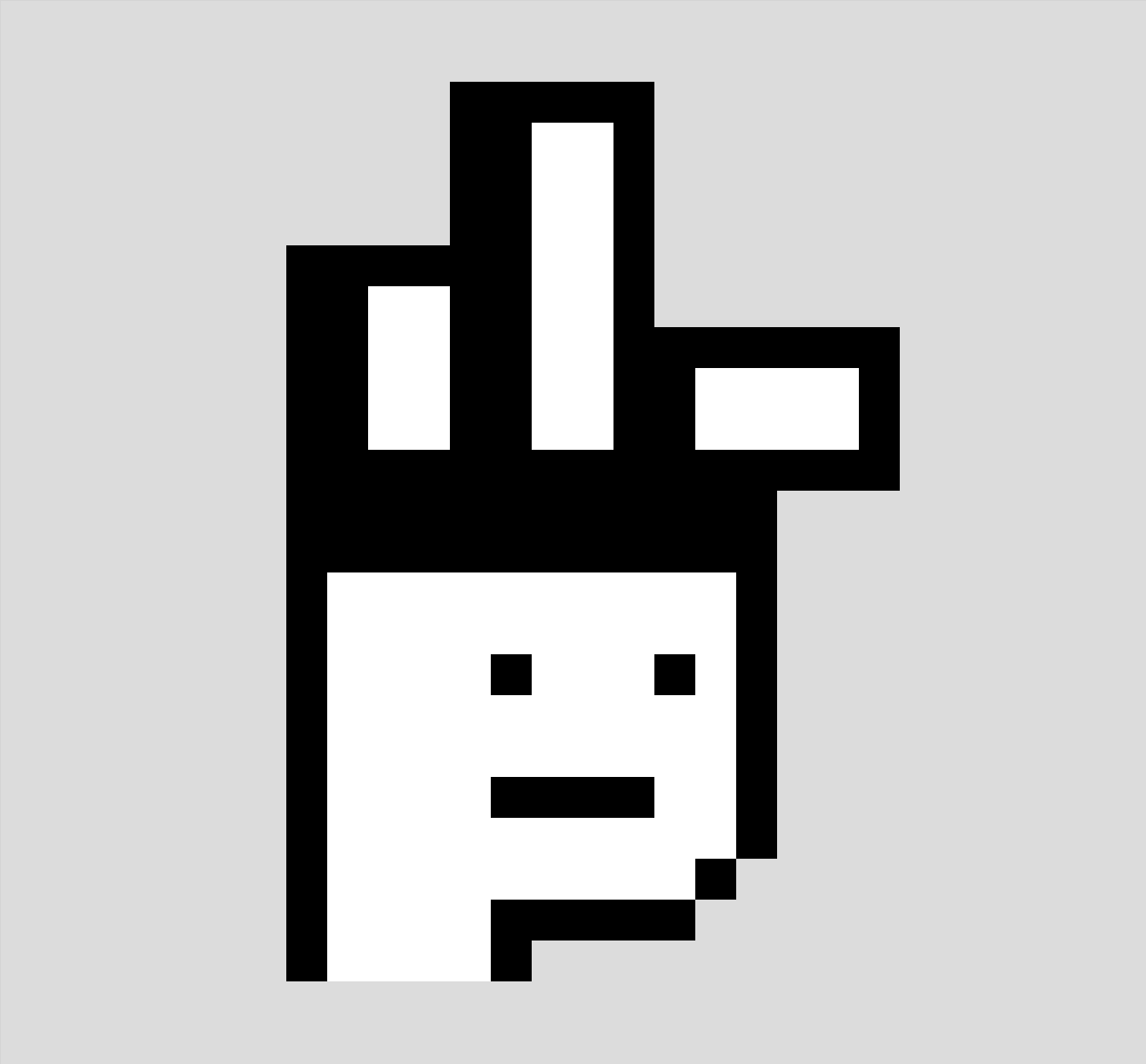
ぼくは最終的に
2時間30分で書けるようになりました。
始めは平行定規から始めると思いますが、徐々にフリーハンドに切り替えてみてはいかがでしょうか。
フリーハンドで書くメリットはこちら。
〇線を書くスピードが早い
〇定規を持つ時間が省ける
〇線の強弱をつけやすい
〇どこでも作図練習できる
とにかく早く書けるというメリットが大きいです。
慣れてくればフリーハンドでもきれいな図面が書けます。
逆にデメリットはこんな感じです。
△手が疲れる
△長い線には向かない
△慣れるまでは線がガタガタ
通り芯や寸法線などの長い線は定規で書いた方がキレイで早いです。
もちろん、どこまでフリーハンドで書くか決まりはないので、自分にあった方法がベストです。
ちなみに、日建学院では製図板さえ持たないフリーハンドの猛者がいました。( ゚д゚ )
道具を減らす
道具は使うものだけに厳選してみてください。
「道具を選ぶ時間」を最小限にできるので作図のスピードアップになります。
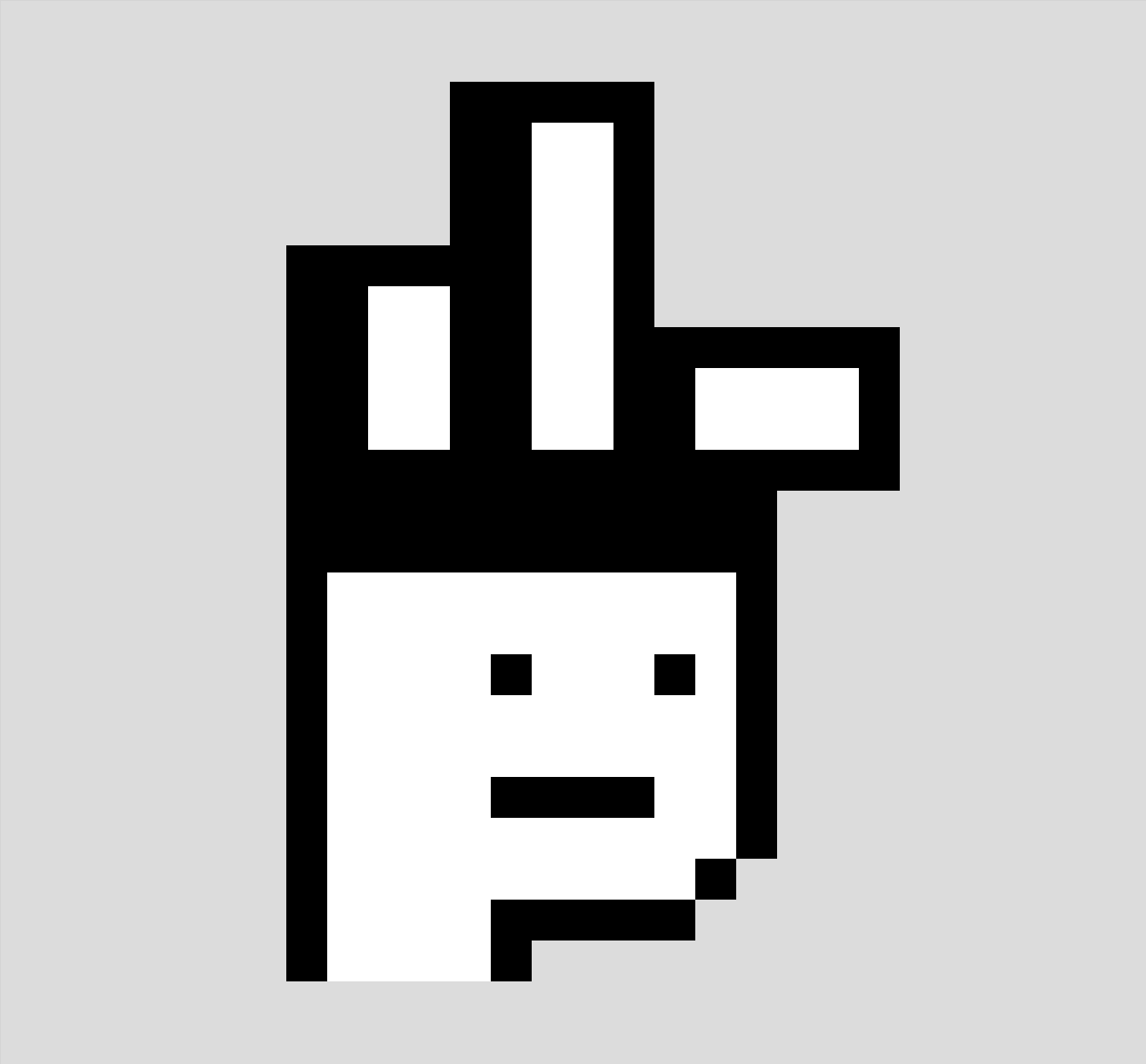
単純ですが、効果は大きいです。
シャーペンや定規は最小限にして作図に集中できるようにしましょう。
オススメの製図道具についてはコチラの記事もどうぞ。

試験会場では道具をたくさん持っている受験生もいますが、気にしないでください。
持ち替える時間がもったいないだけです。
図面の質にこだわらない
図面は、なにを書いてるか分かればいい。
文字がキレイなら見栄えは良くなるので細かい部分は気にせずに進めましょう。
・下書き線は消さない
・寸法の点は○ではなく/
ちょっとした意識で作図は早くなります。
また、作図時間を短縮できればエスキスや記述に時間を使えるので、他の受験生より対応力が上がります。
通り芯は3回チェックする
エスキス通りに作図しないと大幅なタイムロスになります。
通り芯の位置が合っているか3回はチェックしましょう。
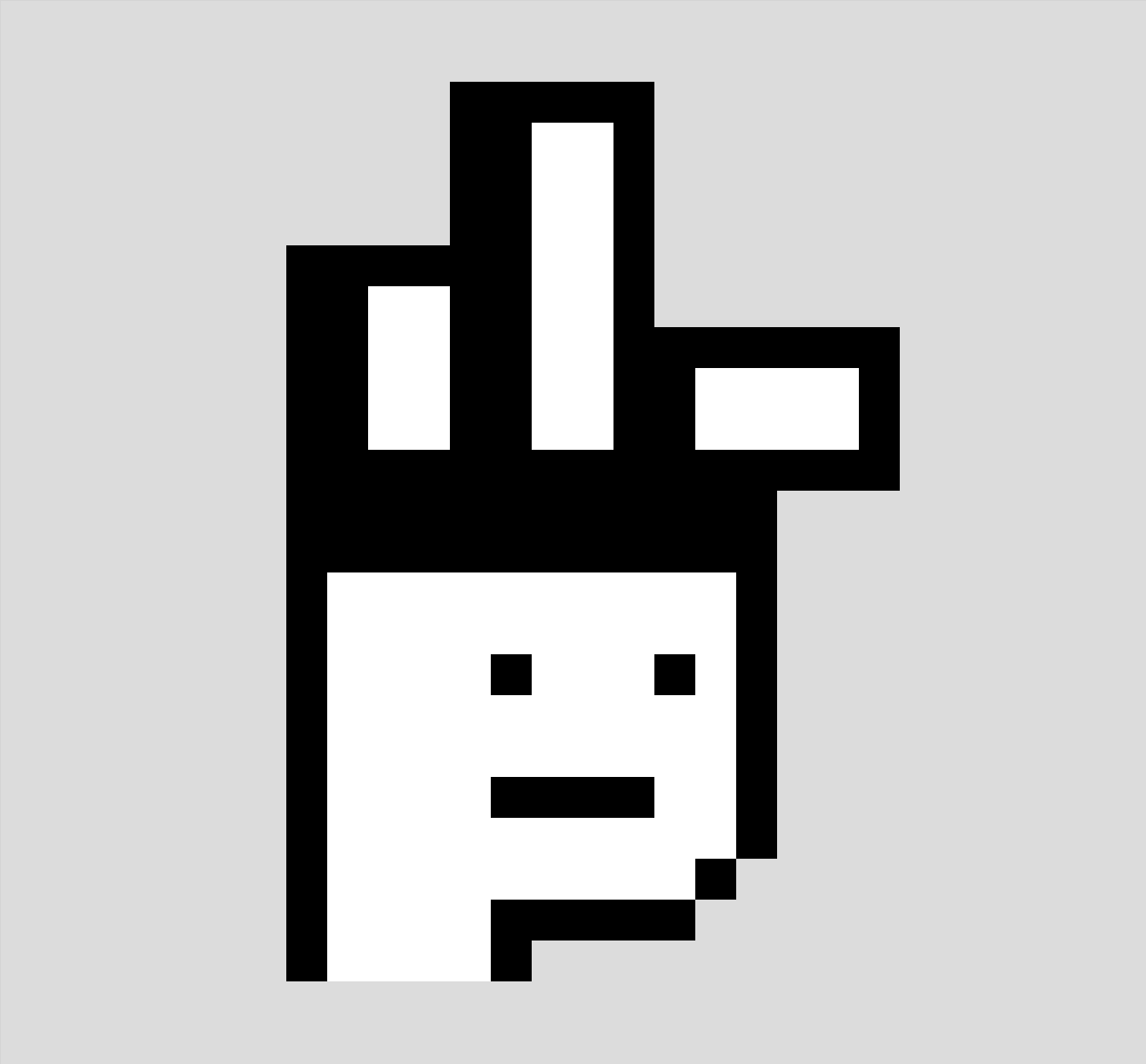
ぼくは模擬試験で
通り芯を間違えて
未完になったことがあります。
途中でミスに気づき絶望しながら書き直しました。
あの気持ちは忘れたいです。(;´∀`)
早く作図を進めたい気持ちもあると思いますが「急がば回れ」でしっかり確認した方が良いです。
問題文を細かくマーキングする
問題文のマーキングは、かなり重要です。
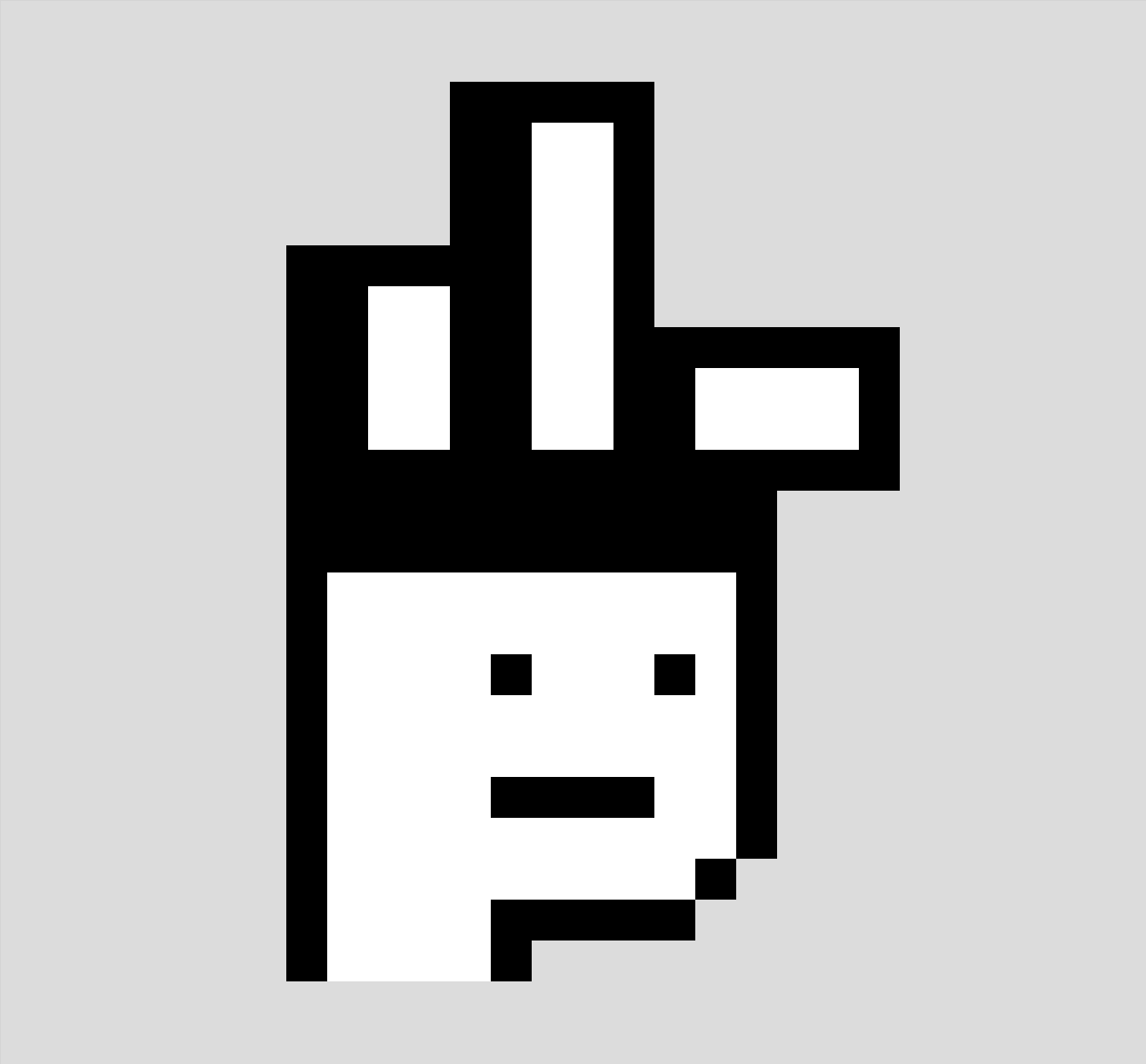
設計条件を見逃すと大減点になるので大事な箇所は細かくマーキングしましょう。
細かくマーキングをすれば見つけやすくなり作図中や完図後の見直しがスムーズです。
おまけ:パーツトレースが最強
色々と話しましたが、作図の練習ならパーツトレースが最強です。
ぜひ、5mm方眼用紙を持ち歩いて空き時間に手を動かしてください。
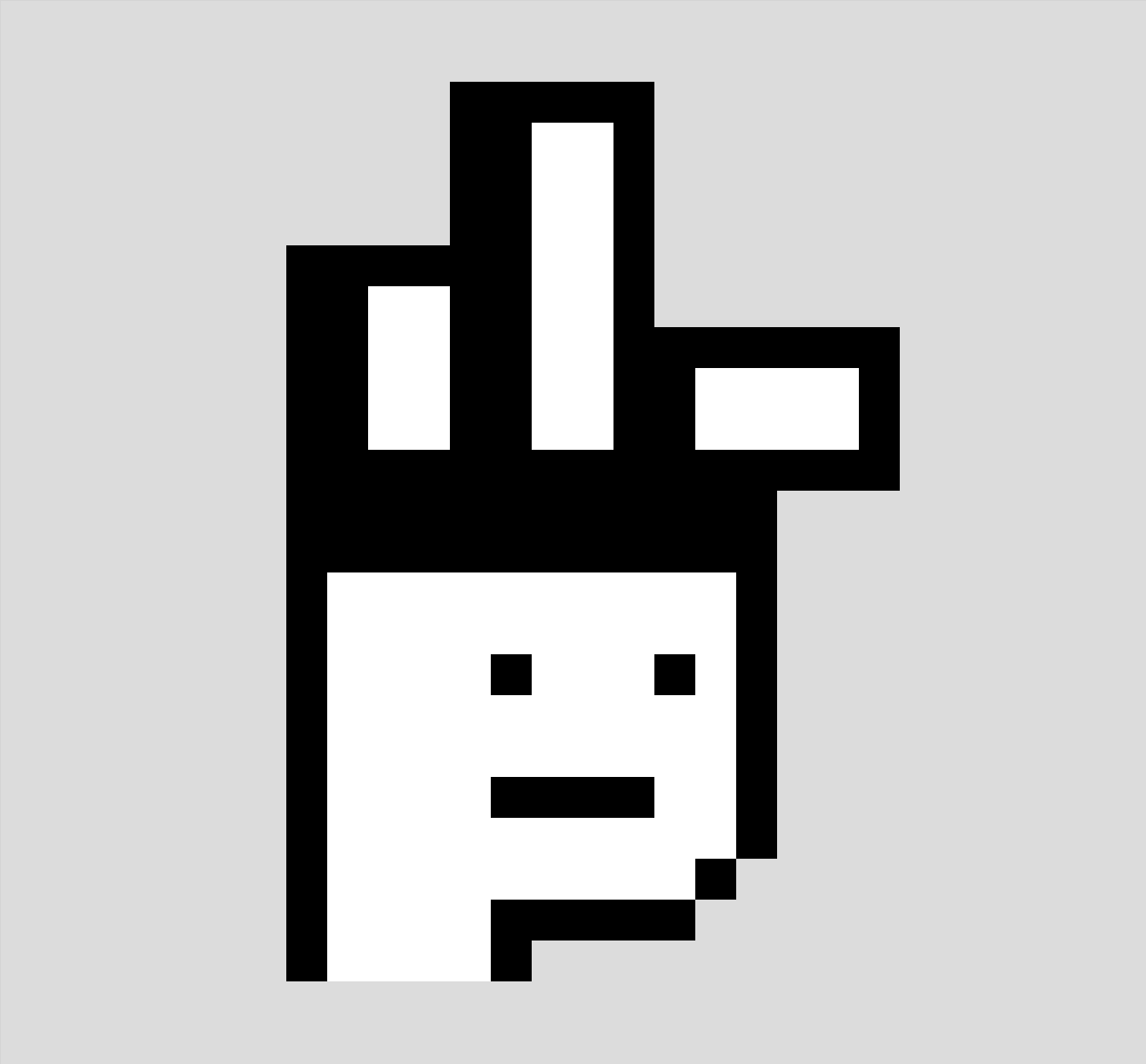
学科試験から製図試験まで3ヶ月しかありません。
とにかく実践を重ねて他の受験生に差をつけましょう。
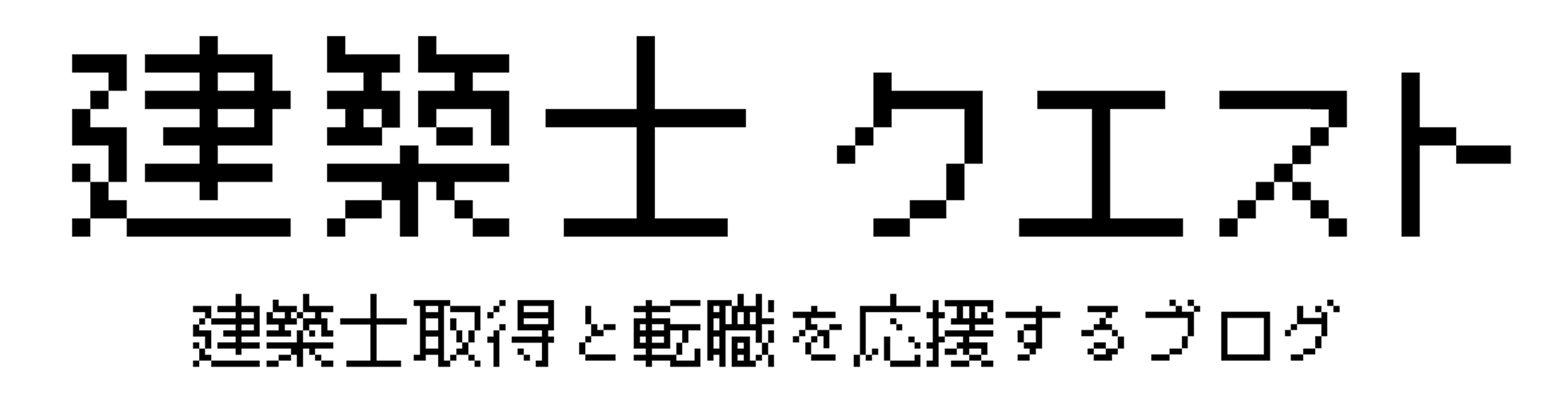
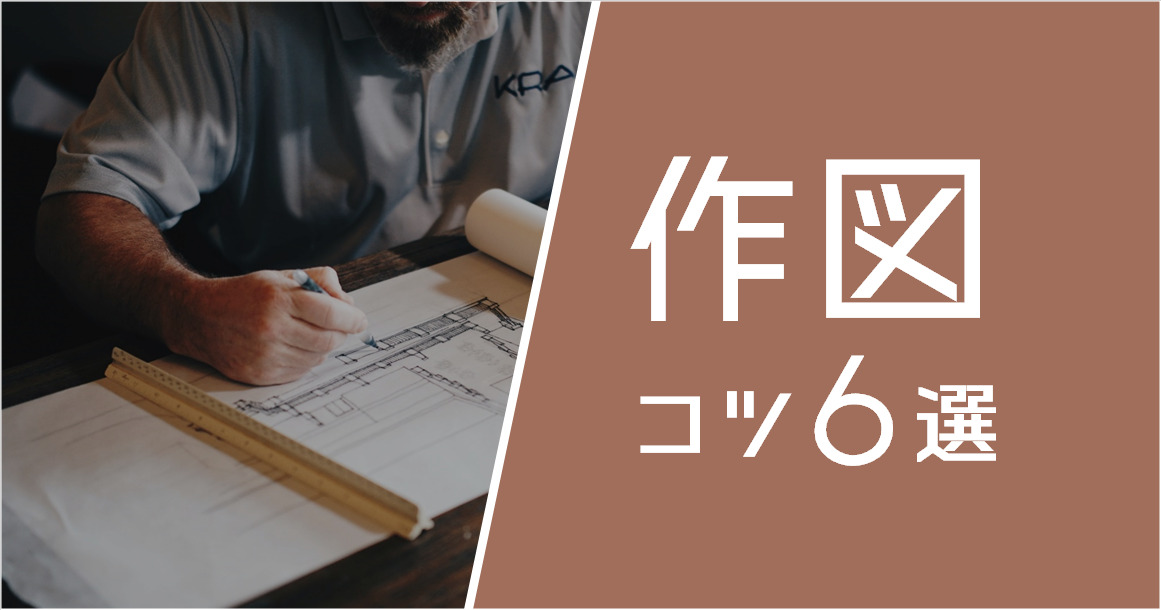

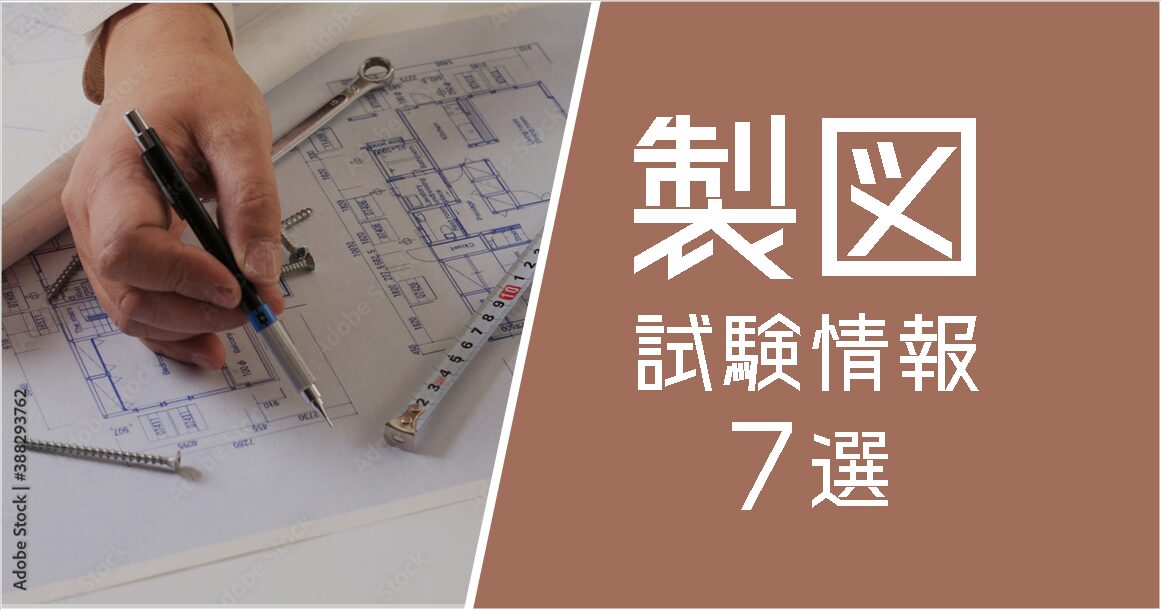
コメント